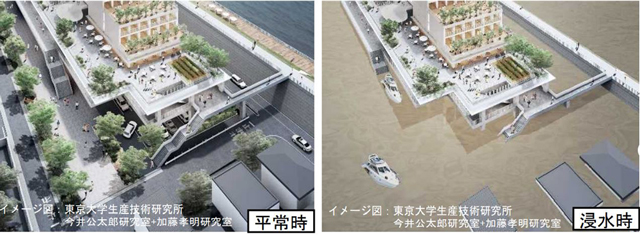東北大災害科学国際研究所の今村文彦所長が代表・呼びかけ人となって、東日本大震災が発生した3月11日を「防災教育と災害伝承の日」に制定しようと、賛同者の募集を始めている。呼び掛け人は今村氏のほか、戸田芳雄・日本安全教育学会理事長、河田恵昭・人と防災未来センター長、林 春男・防災教育チャレンジプラン実行委員会委員長、平田 直・防災教育普及協会会長、松浦律子・歴史地震研究会会長。2022年3月11日からの政府制定をめざして働きかけていく……
災害教訓
2011年(平成23年)3月11日14時46分ごろ、三陸沖、牡鹿半島東南東130km付近、深さ24kmを震源とするマグニチュード(M)9.0の超巨大地震が発生した。東北地方太平洋沖地震と名付けられ、東日本大震災を引き起こす。
この地震は、これまで国内史上最大規模と記録されている1896年(明治29年)6月、明治三陸地震の8.5を遙かにしのぐかつてない規模の地震で、宮城県栗原市の震度7をはじめ宮城県、福島県、茨城県の各地に震度6強の揺れをもたらし、岩手、宮城、福島、茨城各県太平洋沿岸部、長さ約500kmにわたり巨大津波が襲いかかった……
14時46分ごろ、マグニチュード9.0という国内史上最大規模の超巨大地震“東北地方太平洋沖地震”が、牡鹿半島東南東130km付近の三陸沖深さ24kmを震源として発生した。
東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機原子炉が建ち並んでいる大熊町には震度6強の強い揺れが襲ったが、揺れと同時に1号機から3号機各原子炉は自動的に緊急停止、外部からの電源は停電で失われたが非常用発電機が直ちに起動、それぞれの原子炉内では冷却装置が動き出した。しかし……
今回、改めて濱口梧陵に触れるのは、いま新型コロナ感染症という世界的な災禍にあって、再びスポットライトが梧陵翁に当てられるからである。
濱口梧陵は防災のみならず、多くの分野で社会貢献を果たしている。以下、広川町の「稲むらの火の館」資料室をはじめ諸文献、そして千葉科学大学・藤本一雄危機管理学部教授による「濱口梧陵を模範として、100年先の危機に備える」などを参考に、その業績の概略をまとめてみよう……
2011年3月11日の東日本大震災発災から1年半を経た2012年9月12日~10月28日、東日本大震災ビッグデータワークショップ -Project 311-」が開催された。グーグル、ツイッター、朝日新聞、NHK、レスキューナウなどソーシャルメディアやマスメディアが中心となって、震災発生から1週間の間に実際に発生した震災関連情報・データを参加者に提供し、参加者はそれぞれの専門性に基づいてそれらデータを改めて分析することで……
岐阜県内の研究者や防災士らが「災害アーカイブぎふ」のホームページを11月28日に立ち上げた。地域の災害史を知って防災に役立ててもらおうという趣旨で進めるプロジェクトで、来年2021年に発生130年を迎える1891(明治24)年濃尾地震について、発災日10月28日の月命日に当たる11月28日に同ホームページを立ち上げ……
『稲むらの火』のトーチリレӦ…
本紙は2020年11月1日付けで「東日本大震災10年を前に、『11月5日〜津波防災の日』」を取り上げました。本年は「11月5日」制定のもととなった「稲むらの火」の主役である濱口梧陵翁の生誕200年でもあることから、これにちなんで「稲むらの火」の教訓の普及に多大な貢献をされてきた伊藤和明氏から、特別寄稿をいただきました。ここに掲載いたします……
東日本大震災以降、毎年11月5日は「津波防災の日」 、「世界津波の日」だ。呼称が2つあるのはまぎらわしいが、「津波防災の日」はわが国で法律で制定された呼称で、2011年(平成23)年3月11日発災の東日本大震災(地震名:東北地方太平洋沖地震)での大津波で多くの人命が失われたことから、同年6月、津波から国民の生命を守ることを目的に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、そのなかで毎年11月5日を「津波防災の日」とすることが決められた……
宮城県は、東日本大震災を受けて県内21市町に計画された災害公営住宅計画(1万5823戸)の整備を昨年(2019年)3月末で終えた。県はこれを機に、大震災からこれまでの国・県・市町その他関係機関における災害公営住宅建設にかかわる取組みに加え,課題への対応についての検証、今後に向けた提言などをとりまとめ、「東日本大震災からの復興 災害公営住宅整備の記録」として作成、同ホームページ(HP)で公開している……
パナソニックは2016年、日々の防災意識を啓発するプロジェクト「毎日が、備える日。」を立ち上げ、推進している。同プロジェクト公式サイトでは、過去の大規模災害発生日が分かる4月始まりのカレンダー「365日 災害カレンダー」を公開しており、誰でもダウンロードできるが、壁に貼りだすには大きすぎ(文字が小さすぎ)のようだ……
直近の報道の見出しに「縦割りの弊害なくし利水ダムも洪水対策に活用へ官房長官」(NHKニュース、8月12日付け)とあった。「国が管理する水系にあるおよそ900のダムは縦割りの弊害をなくし、洪水対策に使えるよう見直した」というもので、ダムが用途に応じて所管する省庁が異なり、治水用のダムは国土交通省、発電用は通商産業省、農業用水用は農林水産省とそれぞれ別の省庁が所管することでの防災上の弊害(2019年台風19号での緊急放流を例に)を是正するというものだ……

-640x350.jpg)


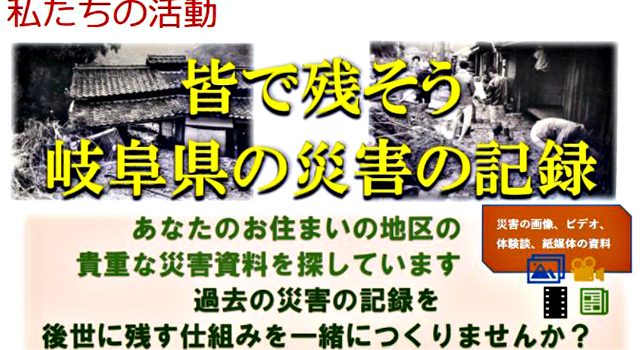
-640x350.jpg)
.jpg)