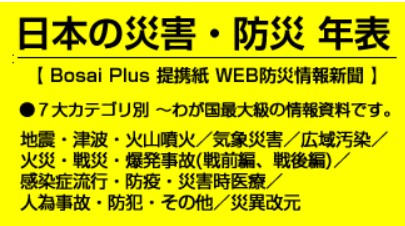東京都は1月27日、2023年度一般会計当初予算案を発表、一般会計は前年度比3.1%増の8兆410億円で過去最大となった。災害に備える「TOKYO強靱化プロジェクト」など、都市機能の強靱化に向けた予算は7397億円と22年度当初比で16.1%増額した。関東大震災から100年の節目となる23年度からの10年間で総額6兆円を投じ、防潮堤のかさ上げや調節池の整備を進める……
【目 次】 ・平家の軍勢、園à…
【目 次】 ・文亀元年越後南ş…
【目 次】 ・幕府、将軍の親ŝ…
防災士研修センターは「防災士制度」発足以来、全国各地で年間80回以上の研修を実施し、自治体や企業。個人でご参加された多くの受講生から高い評価と信頼を頂いております。防災士研修受講修了者のうち、約半数の方が当センターの研修を受講されています……
ペット保険シェアで知られるアニコム損害保険株式会社が、2022年12月、ペット防災専門の情報サイト『どうぶつ防災図鑑』をオープンしている。
災害時にもっとも守らなくてはならないのは、命。それは人もペットも同じで、万が一のときに「ペットを置いて自分だけ避難はできない」と飼い主とペットどちらも被害にあってしまう、あるいは泣く泣くペットを置いていく…そうした事態を少しでも減らしたいもの……
法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社(東京都港区)が、『公民館における災害対策ハンドブック 第3版』を昨年12月23日に発刊した。公民館に求められる平時の防災対策だけでなく、災害対策に備えて事前に準備すべき事項、避難所運営等の対応について、場面ごとにポイントをわかりやすく解説した1冊……
午前0時を人類滅亡のタイムリミットに見立て、それまでの残り時間を象徴的に示す「終末時計」(英語:Doomsday Clock)は、1月24日、世界の現状が「前例のない危険な時代」だとして、これまでで最も短い「残り90秒」に更新された。米国の科学雑誌が毎年発表する「終末時計」は去年は「残り100秒」だったが、これまでで最も人類の滅亡に近づいたと警告している。その主な要因は昨年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻で、ロシアが核兵器の使用をほのめかしたことにある――
日本海溝・千島海溝地震について2022年9月に防災対策推進基本計画が見直され、積雪寒冷地の課題への対応など内容が拡充されたのにあわせて、先ごろ、道の地域防災計画が修正された。具体的には、冬季に千島海溝や日本海溝で巨大地震や津波が起きた場合に備えて、防寒機能を持つ避難所への2次避難も想定したハザードマップの作成や、緊急輸送道路、避難所へのアクセスの道路の優先的な除雪体制の確保、また厳しい寒さや大雪となった場合の高齢者や障害者など要援護者の安否確認や、除雪支援体制の整備などが盛り込まれている……
防災に関するデジタル技術・ICT(情報通信技術)として、住民レベルでの既存のサービスシステムとしては――エリアメール・緊急速報メールを活用した災害警戒情報の提供、地上デジタルTVを活用した災害情報の配信、ワンセグ放送を活用した災害警戒情報の配信、同報系防災無線での災害情報・避難情報の提供、災害用伝言ダイヤル・伝言サービスでの安否確認、防災メールによる災害警戒情報、ラジオによる災害情報・避難情報の配信などがある。
だが、あえて「防災DX」という場合、これらを統合した、より使いでのあるシステムがめざすべき「防災DX」像となる……
改めて、防災の「DX」とはなにか――近年、防災情報システムやアプリを活用した防災ソリューションなど「防災のデジタル化・ITC化」は進んでいるが、それらはあくまで「DX」のための手段であり、「DX」がめざすところは「防災・減災=災害から人の命を守り、財産を保全する」ことにあるはずだ……
東日本大震災後、またICTの進展を背景に、官民において「災害情報システム」の標準化をめぐる動きが急となった。つまり、災害応急対策を決定・実施するにあたって、災害に関する情報をいかに的確かつ迅速に、収集、伝達、そして共有すべきかが防災・減災に向けた重要課題となったのだ。
その研究開発の成果として防災科研は、2016年熊本地震、2017年九州北部豪雨に対して「府省庁連携防災情報共有システム(SIP4D)」を適用……